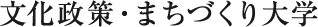お知らせ
総合学術データベース:時評欄(80)ホームページ用;「日本経済の総合的な研究書が登場した」
現代日本経済の総合的な研究書は意外に少ない
私たちは、日々、厳しい経済生活の中で、苦労しながら過ごしている。
それだけに、「この厳しさ」をもたらしているものは何だろうか、と、考える機会も多い。
日本経済に関する、雑誌や、新聞記事や、入門書を読みたいと感じる方々は多いのである。
しかし、不思議なことに、日本経済の実態を知る上での「最適な入門書」を探してみても、意外なことに、そのような本はないのである。
そのような、折には、書店で、入手しやすいものとして、『週刊 経済誌』を手に取られる方々も多いのではないか。
同時に、これらの週刊物の常であるが、ビジネスの現場で「役に立つ」情報が読者から求められるためであろうか。
いきなり有望経営者のメッセージが飛び込んだりしていて、経済の入門としては、強烈な印象があっても、分かりづらいのが残念ではあるまいか。
ここには、経済の世界は没入しておられる方々には通用する独特の言語があり、かえって、一般人には近づきにくいのかもしれない。
ながらく、経済学の教育に携わってきたが、大半の学生諸君にとっては、「よい入門書がありませんね。執筆されれば、売れるでしょうに」と、からかわれる始末である。
このような時に、若手中心の「現代日本経済に関する研究書兼入門書」というべき内容の書物が出版された。
それが、小山大介・森本壮亮編著『変容する日本経済-真に豊かな経済・社会への課題と展望 The transforming Japanese economy』鉱脈社(880-8551 宮崎市田代町263番地 0985-25-1758 http://komyakusha.jp)、2022年刊行。総頁数:1-266ペ-ジ、である。
序章から見る本書の特徴
本書は、次のような構成と、執筆者の分担が行われていた。序章では、本書の特徴が、よく、表されている。
序章 転換期であるコロナ禍の今、日本経済を考え直す(森本壮亮 立教大学)この論文における最初のタイトルは、「1. 崩壊した『一億総中流』」であった。
この表現は、本書の特徴をシンボル化している。
すなわち、第二次世界大戦後、農地改革や独占禁止法、中小零細企業振興による公正競争環境が法的に整備され、労働者の勤労による生活の自立が試みられた中で、農林漁業・製造業・サービス業を問わず、職人型経営・中小零細規模の多い日本経済システムが、何をもたらしたのか。
それは、端的に言えば、「世界初の、経済格差の少ない中流社会」に向けての動きを生み出した。
本書で、森本氏が担当された、第2章 日本経済の歩み においては、戦後復興期とされる、1945-54年に、財閥解体・労働の民主化・農地改革が行われたことを的確に指摘されている。
このような戦後における「経済の民主化」を推進したのは、世界大戦中は厳しい弾圧の対象となってきた日本の労働組合活動、財閥企業の下請けに甘んじてきた中小零細企業群、そして、自治の伝統を持つ、日本農民層の寄生的な地主支配への抵抗と自らの手に農地を取り戻す活動であった。
さらに、当初、アメリカ占領軍には、1930年代に、アメリカ合衆国で、ニュ-ディ―ル政策を担った公務員が日本占領に関わったことがあったので、彼らは、日本の経済民主化に取り組む機会があった。同時に、戦争直後から戦時補償のための赤字公債の乱発が続き、中央銀行による紙幣の乱発は、700倍と呼ばれる猛烈な物価上昇を招き、いわゆるハイパ-・インフレ-ションが日本市民の生活を急襲した。
このすさまじいインフレ-ションを克服する道は、新憲法によって保障された「最低限度の文化的な生活」ではなく、市民の預金を根こそぎに収奪する預金封鎖措置や、市民生活を犠牲にする超均衡予算であった。
日本市民は、太平洋戦争による犠牲者だけでなく、当時の国家破産を容認して「預金すら奪われる」インフレ抑制策によって、市民の大多数が極度の貧困状態を体験させられた。
この厳しい体験を経て、日本の市民は、生活保護制度や、医療保険制度、年金制度などの必要性を強く認識し、先の「経済の民主化」は、時期を大幅に遅らせ、市民生活の確保の動きは、1961年、国民皆保険制度と国民皆年金制度を実現するに至る(48ページ)。
他方、1950年に朝鮮戦争がはじまると、占領軍は、「アジア人をアジア人と戦わせる」戦略を採用し、それまでの「経済民主化」から、日本を再軍備させる政策を開始する。警察予備隊の名目で、現在の自衛隊を整備し、財閥は重工を中心に合併を図り、企業集団化を推進し、「系列」と呼ばれる名称のもとに旧財閥グル-プは復活を遂げた。
さらに、資本力の大きな企業は、「日経連」と呼ばれた経営者組織を発展させて、経営権を支配し、反対に、経営における労働組合の力量が次第に低下してゆく。経営権をめぐる労使関係は、欧米の場合のように、対等な関係ではなく、経営者優位に進行した。
農業は協同組合組織としては発展したが、農民自身が商業や製造業、サービス業などに進出して、地元を経済的に支える活動は衰退し、農林漁業は専門職者に担われる兼業領域を除けば、次世代、大多数の住民が労働力として都市に流入する時代を迎える。現代にまで継続してきた、「過疎地」「耕作放棄地」の出現である。
政治の世界においても、それまでは、戦争犯罪の罪で追放されていた政治家たちが「追放解除」によって復帰し始め、現行憲法を「おしつけ憲法」などと評して改正を求める活動が開始される。
しかしながら、厳しい戦争体験、とりわけ、大空襲や沖縄戦、広島・長崎への原爆投下などの体験をもつ、日本人は、アメリカ合衆国政府の意図にもかかわらず、平和憲法を守る世論を背景に、戦時統制経済への反省から、営業の自由が持つ、真の意味を理解しており、戦後の地方自治制度を生かして沖縄県などの基地負担軽減を政府に要求してきた。
さらに、情報社会による分散型システムへの志向は、民衆の自治意識を高め、強める方向に作用した。
ソ連中心の社会主義体制における崩壊にもかかわらず、資本主義経済体制が危機を迎える
1917年のロシアにおける社会主義革命、それに続く、ソ連中心の社会主義体制は、多くの隣接諸国や地域を統合し、安定した力を得て、アメリカ合衆国を中心とする資本主義体制と「平和共存」をも経験できる状況が生み出された。
この過程で、各地域、市民の間で、「自由と民主主義」への要望が高まる。彼らは、それまでのスタ-リン体制に象徴される、「強固な官僚主義化」を是正しようとした。
1990年には、指導者、ゴルバチョフが、ソ連に大統領制を導入し、共産党の主導的な役割を解消する法改正に踏み切る。もともと、分権化を基本原理としていたソ連邦システムは、加盟諸国が一挙にロシア統治地域から離反し独立していった。
その結果、西欧社会における経済統合に合流する動きも表面化し、その過程で、ソ連社会主義体制は崩壊してしまったのである。旧ロシア地域では、新たな社会主義を目指す試みも台頭はしたが、市民社会として、市民の総意を結集して智慧を集める習慣を、すでに、失っており、新たな社会主義の道を発見できないままに、「資本主義復活」の傾向が強まる結果となった。
ベルリンの壁の崩壊や、チェルノブイリ原発事故が社会主義社会の権威を著しく傷つけたことも、これに拍車をかけた。これに対して、中国の社会主義体制は、天安門事件などの厳しい経験を経ながら、一方で、一党独裁を放棄せず、他方で、私的所有を認めて、経済における営業の自由権を「創造性を生み出すもの」として認めてゆく。
このような私的所有を容認する社会主義は、新たな実験として、ある意味での、「自由と民主主義」の価値を、欧米側と調整する余地を残した。
現在では、この実験が成功して、中国社会主義の権威が周辺諸国に及び始め、経済協力の範囲が急速に拡大しつつある。このような状況の下で、現指導部は、中国市民の総富裕化への方向を語り始めた。それには、富裕層への課税強化、非営利組織の育成、そして、寄付などによる自発的な格差解消への道である。
ソ連に代わる中国社会主義は、1990年から2008年までの期間には、資本主義体制と社会主義体制との共通基盤、私有制という共通基盤の下で、平和裏に共生し得るかのような状況が生み出されたのであった。「自由貿易体制の下で発展する社会主義国」の登場である。
今後は、世界市場で強権的な政治体制が次第に後退し、あるいは、崩壊して、私的所有のもつ創造性や、企業活動の価値が認められ、自由と、議会制民主主義の価値が見直されるのではないか。そして、「市民による新たな文化創生」の可能性が高まってきた、との期待感も生み出されたように見えた。
ところが、ソ連における強権的な政治体制が崩壊して、自由や民主主義の価値が見直された、その瞬間に、今度は、自由と民主主義をもたらしたかに見えた、「資本主義経済を基軸とした政治の世界」は、その正反対の「独裁的で抑圧的な体制」に変化を始めたのである。
その契機となったのは、本書によれば、2008年の、「リ-マン・ショック」であった。
この大きな不況の嵐は、それまで、順調に見えた資本主義経済や、それを支えた、グローバルな技術交流、貿易体制、自由な資本移動や各地の資源開発などを根本的に変化させた。各国の「エゴ」とも言いうる閉鎖的で「自国中心主義」への転換、さらには、独裁的な権力の復活、思想的には、長らく、封印されてきた、右翼思想の台頭をもたらしたのである。
トランプとプ-チンの登場-右翼勢力台頭の背景
そのシンボル的な存在が、アメリカ合衆国のトランプ政権と、ロシアのプーチン政権の登場や存続の可能性である。もともと、資本主義経済には、帝国主義的で、閉鎖的な側面があることは、多くの研究者が指摘してきた。
とりわけ、イギリスの思想家、J.ラスキンの後継者であった、J.A.ホブスンは、20世紀の初頭に、『帝国主義論』初版を出し、1938年に、二つの世界大戦後に改訂版を出版した。数ある帝国主義論の中でも、古典中の古典である。
彼は、1938年の改訂版で、
「資本の生産力が培われすぎてきたこと・・・過度の蓄積と不十分な消費があった」こと、
「国内需要を上回る資本主義的生産過剰」の存在こそが諸国家の帝国主義志向を生み出す根源であると指摘した*。
*J.A.ホブスン著・矢内原忠雄訳『帝国主義論』(上)岩波書店(文庫版)、1951年、「1938年版への序文」12-13ページ。
確かに、アメリカ合衆国のトランプを支持したのは、過剰設備を抱え、失業や過少消費に直面した旧自動車産業の労働者やホワイトカラ-層であった。ある意味では、格差の底辺に落とされた人々が、自国第一主義の右翼的指導者を支援したのである。
この傾向は、第二次世界大戦前、ドイツのヒトラ-登場を支えたのは、過剰設備を抱えた経済と、右翼勢力に導かれ、失業や過少消費に直面した労働者や中産階層であったことを想起させる。
当時、ドイツにおける政権の座にあった、社会民主主義者は、パ-ペン計画と称して、過剰な設備をスクラップ化して、最新の設備に取り換えようとし、ますます、大量の失業者を生み出していた。
日本においても、当時の近衛内閣は「日独伊防共協定」を結び軍部の中国における侵略戦争を容認した。この動きの背景には、日本経済における設備過剰と失業や過少消費が存在していた。
格差拡大を防止し、解消するにはその動きは、本書の序章によれば、次のように表現することができよう。
(1)「格差の拡大」の実態 1990-2000年に非正規雇用、特に「派遣」の拡大により正規雇用にも賃金低下が及ぶ。
(2)減った賃金、増えた企業利益
日本の生活調査=1994年、664.2万円から2018年に、552.3万円まで、20%低下。
日本の企業利益=1990年代後半、GDPが停滞する中での利潤の確保が進む。
労働分配率が60%を超え始め、製造業においては、65-70%に及ぶ(法人企業統計による)。
資本金規模の大きな企業に対して、総資本営業利益率の増加(49ページ)と内部留保の急増をもたらす。
この過程を推進したのは、カルロス・ゴ-ンのような経営者による合理化や政府の規制緩和策、とりわけ、労働者派遣法の改定であった(82ペ-ジ参照)。
(3)政治と分配の変化 このような労働分配率の資本側への有利な配分は規制緩和政策、大企業減税などへの世論同意などをもたらし、労働側に不利な状況を固定化させた。
(4)合成の誤謬 国際競争の場における日本大企業の生き残り策は、各の企業ごとに、大規模設備投資による量産システムを採用するしかない状況となった。
過当競争状態は、調整不能な事態となり、「各々の企業は、利益を上げるが、資本全体としては、利潤率が低下し、資本が過剰となって『カネあまり』が常態化」する。日本銀行が通貨を増発しても、使うこができない状況が生まれた。K.マルクスのいう「利潤率の傾向的な低下の法則」が、21世紀の日本経済において表面化してきたのである。
マルクスはエコロジ-の世界だけではなく、現実の経済研究においても、有益であるようだ。
もしも、この法則から逃れられないとすれば、どうすればよいのか。「本書を紐解き、日本経済の現状を批判的に捉えることで、持続的社会の実現や豊かな社会に向けた取り組みへの理解が深まれば」というのが、編集者からのメッセージである。
本論は、過剰設備を抱え、リストラ、失業、過少消費に直面する日本経済を、どのようにして環境問題や格差・貧困の実態を踏まえて着実に改善し、持続的な社会の構築、豊かな社会への道を探る。結論を急がず、着実に議論できる土台を構築するのが、本書の目的である。
第一部 政治経済情勢の「常識」が変わる
1章 両極化する世界に生きる=小山大介氏
2章 日本経済発展史、日本型の成立と解体=森本壮亮氏
第二部 変質する日本経済-経済・産業政策の本質
3章 失われた30年-構造変化=森本壮亮氏
4章 キャスレス経済=田添篤史氏
5章 貿易変質と通商政策・国民生活=小山大介氏
第三部 保障政策、地域政策を問い直す
6章 劣化する労働環境・「働き方改革」=中野裕史氏
7章 ベ-シック・インカムは社会保障の核となり得るか=瀬野陸見氏
8章 国民皆保険制度は本当に持続的か-制度危機の処方箋の検討=瀬野陸見氏
9章 農山村の内発的発展と財政-林業・木材産業をケースに=白石智宙氏
第四部 日本の新たなる国内課題と、社会のあるべき「姿」を探る
10章 経済成長・格差・少子高齢化=金江亮氏
11章 民間非営利組織の営利化、営利組織の非営利化-NPO,社会的企業、CSR,EGS投資ゆくえ-=梶原太一氏
12章 情報化、IoT時代がもたらす未来社会の「姿」-GAFAで変わる市民生活と企業活動-=小山大介氏
終章 転換期にある日本経済-グローバル化と自由主義の先へ=小山大介氏
この内容から理解できるのは、現在の日本経済が若者たちの流行ファッションだけを見ていると、欧米の諸外国に比べて、「1億総中流」であるかのように見えてくる。しかし、現実には、この願いは「うわべ」だけの話であって、中流というのは幻想にすぎず、「崩壊」していること。
つまり、日本市民の間では、とりわけ、バブル崩壊後の1990年代以降、非正規雇用制度が拡充され、雇用機会や職業をめぐる市民同士の生存競争が激しくなってきた。「お前のかわりはいくらでもいる」というセリフが流行し、互いに「足を引っ張られて」厳しい生存競争に巻き込まれた。
「戦後の経済民主化」によって自立できたはずの日本市民は、このなかで、「中流のはずの層」が全部にわたって低所得層になってしまったことが示されている。
これは、欧米諸国の賃金を得て生活している層が、平均で見ると、賃金の上昇傾向がみられるのに対して(このことは低所得層が欧米で減少していることを意味しないが)、著しい「日本的な特徴」となっていた。
そして、その一方で、日本における大規模企業の内部留保金額は膨張をつづけ、「万一の危機に備える準備金」は、史上最高の水準に達している。他方で、中小零細企業の経営状態は年々悪化していて、日本型「二重構造」は、回復が難しいくらい深刻化してきた。
そして、生存競争が激しくなれば、宮本常一が「忘れられた日本人」のなかで、解明したように、長い歴史の中で発展してきた、日本市民における自治の伝統が忘れられることも多い*。
*宮本常一『忘れられた日本人』岩波書店(文庫版)、1984年参照。
とりわけ、大都市では、個々人が「話し合い」によって市民の間に通用するル-ルをつくり、公正に競争しあって、互いを支え合い、高め合う関係が壊されてくること。これが、経済の現実の姿であることが、本書では、具体的な数字を通じて実証されている。
本論では、著者たちが、日本社会の持続的な発展や、豊かな社会への方向性を模索されている姿をご紹介し、併せて、今後の課題などを、ともに、考えてゆきたい。
(©Ikegami,Jun.2021)