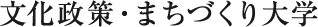お知らせ
総合学術データベース:時評欄(70)ホ-ムペ-ジ用;池上惇「現代産業における融合と 分業-工場法・公害防止法・循環促進法を手掛かりとして-」
はじめに--現代産業における「融合と分業」
現代産業において、従来の「分業と協業」の関係を深める研究として注目されるのが「融合と分業」の大変化過程である。
現代産業論の展開として、この研究に着手されたのは、十名直喜教授であった。同氏は、「21世紀型産業システムへの視座-持続可能な循環型発展モデルの創造に向けて-」において、産業の実態における「分離・分化から再結合・融合化へ」および、新たな研究方法として、「システムアプローチ」を、提起された。
同氏が提起された、①現代産業における「分離・分化から再結合・融合化へ」の実態と、②研究方法としての「システムアプローチ」について、その大要を法制度の整備という視点から研究する。
「分離・分化から再結合・融合化へ」-最初の契機は工場法-
資本主義経済が利潤追求を最優先にした時代においては、営業の自由という基盤の上で、「規模の経済」を追求することによって量産型システムを採用することが普通に行われてきた。そして、規模の経済は巨大企業の誕生を生み出して、営業の自由という基盤をも揺るがす状況に至る。公正な自由競争ではなく、巨大企業が中小零細企業に対して、価格競争を仕掛け、規模の経済を利用して市場における独占的地位を確立し、下請けシステムを定着化させ、「食うか、食われるか」などの熾烈な生存競争の激化を伴う事態である。ここから、いわゆる、大量生産・大量消費・大量廃棄と呼ばれた生産システムが独占的な地位を確立して市場を支配する状況が生まれる。この過程では、自然環境や環境資源・生態系などを無視して利用し環境問題を激化させる。同時に、独占的な利益を享受する一部の資産家と、多数の貧困者途への社会の分裂が進展し、社会問題が激化してゆく。さらに、世界中、どこからでも、「より安いコスト」で、生産要素を購入する流通チェーンが支配するので、巨大企業を擁する先進諸国と、コストとして安価な労働力や自然資源を利用されてしまう発展途上諸国との格差も拡大される。
このような「巨大企業の株主に利益を独占させる大量生産システム」は、自然との関係においても、社会との関係においても、公害問題や格差・貧困問題を激化させる傾向がある。
なぜかと言えば、「規模の経済」を巨大営利企業が追求すると、大規模な設備・装置への投資と自動化による人員削減が必要とされる。ここでは、生産システムにおいて、本来、「主人公」「主体」であるはずの人間は、単なるコストとして評価され、機械が自動化するにつれて「機械のリズム」に合わせて仕事をする「機械に類似した作業(分業の原理によって細分化された作業)を担う人」として扱われやすい。経営者も労働者も、「コスト化」され、より効率的に機械を活用できる人材が経営者や管理者として評価されるようになる。
著名な喜劇俳優、チャップリンが演じた、「モダン・タイムズ」は、機械のリズムに合わせて仕事をせざるを得なくなった人間が辿り着く、究極の姿を描いている。それが、ベルトコンベアの速度に合わせて自分の頭脳と身体を使い果たし、食事さえも、自動機械のお世話になり、耐えられなくなって、逃げだし、レストランでサービス労働を提供するが、ここでも、移動機械のお世話になり、泣き笑いしながら働くことになる。
ここで、描き出されたのは、「機械と人間の生存競争」であり、機械との競争に敗れて、人間性を喪失し、仕事における潜在能力さえも奪い取られる現実がある。機械・装置は「経済的資本のシンボル」となった。
分業化への傾向が機械化・自動化と結合されると、本来の人間存在と「コスト化」された人間との間には、深刻な矛盾が生まれ、これが、人間の判断力などに「障がい」を設ける。このために、常識や正常な理解力を失い、人と自然との関係が見えなくなり、人が貧困化しても支援しようともしない風潮を生み出す。人間相互の礼儀なども衰退して、「砂をかむような」厳しい人間関係が生まれてくる。個々人が孤立化し、相手を加害者と感じて殺傷するような事件が多発する。
そして、これらが、環境問題や社会問題を引き起こす原因となるのである。このような「機械化された人間」は、当然の結果として、自然との関係においては公害を生み出す結果となり、社会との関係においては、格差や貧困を生み出す原因となるであろう。
資本主義経済や経営の本質とも言うべき、このような深刻さに対して、人類は、どのように反応してきたのであろうか。
それは、まず、19世紀の後半に、世界的に普及した「工場法」の制定である。この法律は「機械との生存競争」によって非人間化された、経営者と労働者が人間性を回復し、「人間が人間らしい生活や仕事を取り戻す」きっかけとなった。
このような意味では、分業や機械の採用によって、細分化された「コスト」としての仕事に人間が従事し、一日の仕事をこなす中で人生が終わるということは、人間自体に、分業・機械化を克服して、人間自体を取り戻す力量が奪われてしまうという深刻な問題を提起する。個々人を政治の主体とする社会においては、このような状況の時に、「人間を取り戻す」ための、法制度を生み出すことは、決定的に重要な意味を持つ。個々人の力量を取り戻して、潜在的な力量を、顕在化させること。そのための第一の条件は、個々人が互いの人権を尊重しあい、一人一人が自由に学習する権利を取り戻すことこそ、その第一歩であった。
工場法には19世紀後半期における、経営者と労働者における非人間的な苦しみを基盤として、経営者活動や労働運動の結果として誕生した。経営者活動としては、イギリスにおける、ロバート・オーエンの市民活動が著名であり、労働運動としては、イギリスにおけるチャーチスト運動(普通選挙権を要求する人民憲章実現をめざす)、フェビアン社会主義運動などが有名である。また、工場法だけでなく、日本において、展開された公害防止市民活動とその成果である「公害防止基本法」、現代の世界的な環境市民活動の影響下に成立する「プラスチック廃棄物を再生利用する‘循環促進法’」など、世界的な規模での市民活動が「人間を取り戻す」契機となってきた*。
*宮本憲一『戦後日本公害史論』岩波書店、2014年参照。
工場法につながる法律は、「工場査察官報告書」として、人道的な医師を中心とした、「人間を取り戻す」世界初の動きを生み出した。
この法律を実行した結果、経営者も、労働者も、「労働時間の短縮による自由時間と自由な空間」を確保できた。さらに、公衆衛生条項や教育条項の支援を受けて、義務教育が実施され、俗にいう「読み書き算盤」に通じた学習人が衛生的な住居とともに誕生したのである。同時に、国によって、工場法の実施についても、大きな差異が生まれた。欧米にも広範囲に残る「スラム地域」の存在は、この事実を象徴していると言ってもよい。
人間が人間らしさを取り戻す動きには、国によって差異があり、このことを踏まえた応答が各国市民に求められる。
基本的な傾向としてみれば、自由な時間と空間は、経営者にも、労働者にも、量産型商品やサービスに対する疑問を生み出し、ラスキンやモリス、日本における、梅岩や尊徳らは、大工業が支配する以前の時代には、支配的であった、職人型工芸産業に着目し、デザインを重視するとともに、商品やサービスの質を考慮し、多品種少量生産システムへの道を拓こうと模索を続けた。
さらには、庶民や民衆の文化的な向上を通じて、自然と共生し、格差や貧困を克服する世論を生み出そうとした。
しかし、彼らの先駆的な思想は、「規模の経済」がもつ、圧倒的な威力には対抗できず、しばしば、少数派や異端者として、貶められた。ラスキンや梅岩らに冠せられた名称は、「ロマン主義」「空想主義」であり、資本主義以前の旧態への郷愁にすぎないとの非難も寄せられた。
ところが、1980年代以降、情報・通信技術が進歩し、生産技術の基礎や消費者における倫理的な傾向が台頭する時代が訪れる。労働時間の短縮に加えて、「働き方」そのものが改革を迫られる時代となったのである。情報通信技術も、それが「機械」である限りは、人間と機械との競争を激化させる。だが、それと同時に、人間の健康とか、生きがいとか、「機械の導入では解決し得ない」人間としての発達の課題を提起してきた。これらは、「失われた人間性を取り戻す」動きを顕在化させた。
人間が人間らしく、自然環境に向き合えば、人間と視線との共生や、人間同士の共生に目を向けざるを得ない。例えば、AIが人間に取って代われば変わるほどに、「人間でなければできないこと」に注目が集まる。
このような「人間らしい人間」が自然環境を見る目は、しばしば、環境問題や格差・貧困問題と連動する。情報・通信技術の台頭は、生産システムにおける技術的な革命をもたらしただけでなく、人間らしい人間が仕事や生活において技術を制御し、自然との共生、人間同士の共生を追求し始めたのである。そし技術が人間を支配する時代から、人間が技術を支配する時代への大転換である。
情報技術の普及に伴って、この動きと「人間を取り戻す動き」が連動するということもできるだろう。
このような動きが現実化するにつれて、多品種少量生産システムは、徐々に、大量生産・大量消費・大量廃棄システムを一歩一歩制御してゆく。その歩みは決して速くはない。しかし、着実である。
多品種少量生産システムが容易には進まない理由としては、この過程では、量産型主体の大規模企業などから大きな抵抗があること。この事実も注目に値する。とりわけ、圧力団体を通じて国家組織が利用されるために生じる中央集権的な動きも決して無視はできない。また、多品種少量生産システムが永続するための基盤として、量産型産業も必要とされる場合があるので、大規模企業ではない、新たな量産型産業が誕生する可能性もある。しかし、それにも関わらず、多品種少量生産システムは、長期的に見れば、徐々に、量産型を制御してゆく。
このような多品種少量型システムへの動きにおける、「シンボル」となったのは、「デザイン経営」の思想である。東においては、「銀座の資生堂」、西においては、「神戸のフェリシモ」、そして、大きな思想的な流れを生み出したのは、GKグループ、田中一雄氏の『デザインの本質』、学術界においては、J.ラスキンや、二宮尊徳の思想を継承した、「文化経済学」「文化経営学」の登場であった。
「システムアプローチ」が意味するもの
他方、十名教授が提起された「システムアプローチ」という、個別化された分業体制を融合させる、新たな方法とは、どの様なものであろうか。この言葉のうち、「システム」という言葉自体は、人類が生み出した、知性の証として、情報革命や産業革命以前から存在していた。古代ギリシャ語にさえ、組み立てるという意味では存在していた。
この語が現代において、積極的な意味を持つに至ったのは、何が契機となったのであろうか。それは、先の、工場法における教育条項が深く関わっていると考えられる。そして、「システム」志向が産業を融合させる推進力となるには、疎外からの回復を実現する法制度の整備が必要であり、その意味では、技術そのもの、とりわけ、情報・通信技術が持つ、「融合の潜在力」が社会問題や環境問題を媒介として「法制度の整備よって現実化する過程」が重要となってくる。
経済社会において、分業化が進行したとき、それが人間としての総合的な判断力などに影響を与え、人間の判断力を制約することを、最初に発見したのは、「経済学の父」と呼ばれた、A.スミスであった。彼は、一方で、分業の社会における役割を高く評価しておきながら、同時に、他方では、「分業の弊害」について語り、それを克服するには、教育制度*の整備が必要であると指摘した。これは、人間が教育制度を構築して、「分業による狭い視野」を脱し、常識によって総合的な判断力を取り戻すこと。この制度の重要性を指摘したのである。
*スミスは、システムではなく、institutions を用いている。この語には、基盤を構築するという意味だけでなく、物事に形や秩序を与えるという意味があり、19世紀20年代には、system と同義に使用されていた。The Shorter Oxford Dictionary on Historical Principles, Vol.1, Clarendon Press, 1973、1085ページ。スミスの原典では、以下のように表現されている。“institutions for instruction for education of the youth and those for instruction of people of all ages”, A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes the Wealth of Nations, 1776.The University of Chicago Press,1976., P.244.
スミスにおける、教育制度などの機能を、現代に継承するとすれば、「システムアプローチ」の主体は「人間そのもの」であり、本来は、各市民が持っている、潜在能力である。スミスの時代には「工場法」は存在しなかったが、人類は、19世紀中葉には、工場法を成立させ、「人間が潜在能力を取り戻す」時代を開始したのである。
このような意味では、労働時間と、諸個人の自由時間を明確に区別し、人間が人間らしく生きる時間や空間を確保する制度、あるいは、システムを確立したことは、人類史上、画期的なことであった。
経済学の発展史において、最初に、工場法に着目したのは、法の制定に奔走した、ロバート・オーエンであった。彼は、しばしば、空想的社会主義者として、批判の俎上に載せられてはいるが、実態としては、自ら政治や議会制度の世界に飛び込み、工場法推進の原動力となっている*。
*宮瀬睦夫『ロバート・オウエン―人と思想』誠信書房、1962年。
システム・アプローチの先駆者のひとりが、アダム・スミスであったとすれば、彼が構想したのは、分業社会の欠点を人間社会のルールづくりによって解決しようとする志向であった。このアプローチの特徴は、人間が主体となって、人間の健康や生きがい、など、人間の潜在能力の発揮を妨げている原因を解明し、それを是正して、人間本来の姿を取り戻すことであった。それは、社会の「ルールづくり」に関する人間能力の発揮であり、「疎外からの回復」を人間自体が実現してゆく過程でもあった。
そして、現代における「労働者と経営者」の「人間性回復」への手掛かりを提供したのが、工場法や、それを査察する医師などの公務員であった。
彼らの持つ医師としての「人の心身」に関わる情報を生かす場が存在する時代が到来した、と言えよう。
このような意味で、システムアプローチは、人間自体がコストではなく生産活動の主体であり、彼らが動かすソフトウエアとハードウエアの総体が「人間が動かす機械」として機能することとなろう。
現代における「システム・アプローチ」が、スミスの文化的な伝統の上で実行されるとすれば、それは、どのような形をとって現れるのであろうか。
今回は、この課題に挑戦する。
(©2021、Jun、Ikegami)