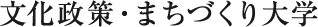お知らせ
池上・総合学術データベース:時評欄(25);「‘適切に使うほど価値が増すモノ’を生み出すには」2019年12月16日
「‘適切に使うほど価値が増すモノ’を生み出す」職人たち
2019年12月2日付の『日刊工業新聞』は、「ひとカイシャ交差点」の記事(4ページ)に、日本デザイン学会会長、慶応義塾大学教授・デザイン塾主宰:松岡由幸先生の談話を掲載した。
この談話のタイトルは、「使うほど価値増すモノを」である。
この時評では、表現を、やや工夫して、「‘適切に使うほど価値が増すモノ’を生み出すには」とした。
松岡先生が、ここで、事例として、挙げておられるものとは、主として、二種類のもので、この時評では、二つのうちの一つを取り上げて検討したい。
その一つは、日本の手工芸品、漆器のように使うほどに酸化反応によって硬くなり色つやもよくなるモノである。また、豊橋筆、熊野筆には、使うほど、生きもののように成長し、職人は、よい毛を選ぶ「目利き」であり、毛の特性を引き出す手わざがあるし、書家の文化力や書道家としての筆遣いの特徴を生かす洞察力や手わざがある。
ここには、化学反応や生物の成長過程をあたかも知っているかのような、素晴らしい職人技がある。化学反応も生命体の維持や発達にとって、欠くことのできないものであるならば、ここで、指摘されていることは、生命を持つ生物と、よく似た進化過程を、本来は、無機的なモノであるはずの漆器や特産筆は「職人との関係性を持つこと」を通じて、示していることとなろう。職人が使う言葉の一つに「心を込めてモノをつくる」とか、「モノに魂を吹き込む」などの表現がある。この表現に従えば、「魂を吹き込まれたモノ」があたかも生命体であるかのように、生物的な変化や進化を体現しても不思議ではないのかもしれない。
なお、ここでは、触れられていないが、日本の大工には、「息をしているかのような壁や、冬は暖かく、夏は涼しい家をつくる」という表現もある。家が呼吸し、まるで生きているかのように、四季の変化に応答しているのである。
職人は、化学や生物学を知らなくても、経験と学習(learning by doing)によって、職人の力量を磨き上げて、職人の人間的な力量として、‘適切に使うほど価値が増すモノ’を生み出す能力を身につけてゆく、と、考えることも出来よう。