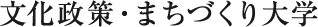お知らせ
池上・総合学術データベース:時評欄(90)ホ-ムペ-ジ用;池上惇「ケインズ革命を超えて」
はじめに‐1979年から1980年にかけてのイギリス留学と古書店訪問
これまで、文化経済学研究と並行して、財政学の研究を行ってきた。
この領域の研究では、超えるべき、大きな山が二つあった。
一つは、恩師、島恭彦先生による『近世租税思想史』の、現代版とでもいうべきものを出版すること。
そして、もう一つは、地方財政論の領域で、大正期における大阪市財政の研究を通じて、当時、急速な発展を遂げていた、大阪経済の実態を解明し、そのなから、現代に通用するものを発見することであった。
前者については、1999年、池上惇『財政思想史』有斐閣、を刊行することができた。
そして、後者については、2022年、池上惇『池上四郎の都市計画』京都大学学術出版会が、世に出た。
これら「二つの山」を越えて、さらに、次の山、より困難な山に挑戦しようと構想を練り上げつつある。
そのなかで、1979年から1980年にかけて、イギリスに留学した時、いま、思い出しても、強烈な学術上の刺激を受けたことは、忘れられない。
当時は、海外への留学制度が国立大学の教員には「50歳までなら」という条件付きで、認められていた時代である。留学するには、各学部から選出された学部長会議の承認を得なければならない。幸いなことに、ご承認を得て、当時は慣例であった、日本で普及していた、イギリスの文化施設で英会話の訓練を受け、日本航空という政府ご指定の国営企業で出発した。
このころは、先達の御推薦状によって、推薦された大学に留学するのが通例であった。
これも、幸いなことであったが、京大の大先輩、森嶋通夫先生が、ロンドンにある、LSE=London School of Economics の教授であったので、先生のご推薦で留学できることとなった。
歴代の学友たちが下宿していた民家をご紹介いただき、ロンドン北方の下宿先に落ち着き、ここで、半年を過ごした。LSEの図書館を利用し、大英博物館の図書館なども活用しながら、古書店を回っては、新たな文献を探し始めた。
そのころの、私の最大の学術的な関心は、先に述べた、二つの山とともに、ケインズ革命を超える、新たな経済学への模索であった。この課題は、かつて、故森嶋通夫先生が追及された課題であったが、先生は、未達成のまま、他界されてしまった。
何とかして、このお志を継承しようとして、目を付けたのが、イギリスの古書店であった。
戦後の古書を調べれば、イギリス人のことだから、ケインズ革命批判を試みた研究人がいるに違いないとの期待感もあって、ロンドンの古書店を歩き回っていた。
いまでも、そうであるが、イギリス人ほど、多様な議論が共生している国はないように思う。おそらく、市民社会としての成熟度が高く、多様な議論を寛容に公正に比較できる目が育っているのではないかと思った。
はたして、古書店には、貴重な文献が眠っていた。イギリスの古書店には、文献を収集した方の、サインが入った文献が多い。そのなかのひとつに、「揺りかごから墓場まで」と
言われた、手厚い福祉国家構想に対して、厳しい目を向け、「重税国家批判」を展開した、コーリン・クラークの文献を発見した。
コーリン・クラークによる、慎重なケインズ革命への疑念
そのころ、新たな学術的な関心は、「ケインズ革命を超える、新たな、経済学体系の模索」であった。
京大で、講義を担当していたのは、「財政学」であったが、丁度、ケインズが、マクロ経済学の基礎を提供し、サムエルソンが経済学の教科書を執筆して、ミクロ経済学と、マクロ経済学を統合したことに、強い関心を持つこととなった。
サムエルソンの教科書では、「政府部門」という、新たな部門が、民間部門や、家計部門と並んで、マクロ経済学の中に、登場していたのである。
言うまでもないことであるが、「政府部門」とは、民間の経済や家計とは、異質の存在である。この部門は、「国家」という「高度に複雑な、研究に値する」存在を前提として成立している。
とりわけ、民主主義国家においては、市民が自立した存在として、選挙によって、議員を選出し、議員の議決によって、法を創る。この過程は「政治過程」あるいは、「市民による意思決定過程」と呼ばれていて、民間の経済や、家計の経済のように、市場を通じて動いているわけではない。
このように、異質のものを、あたかも、経済行為を行うかのように、「政府部門」として取り扱って、よいのだろうか。
このような疑問であった。
疑問の背景にあったもの
このような疑問が生まれてきた理由は、当時の財政学会の主流的な発想への疑問と関係していた。
当時は、福祉国家を支える財源の議論が活発であったので、「福祉国家を支えるには、市民が一定の税負担を覚悟する必要がある」との議論が行われていた。
その典型的な理論は、「一般消費税を導入して、福祉財源とする」という議論であり、とりわけ、北欧諸国が付加価値税を導入して、福祉の充実を図ってきたのを、日本社会から観察してのご議論であった。
そこには、クラークが提起したような、「国民所得のうち、40%を超える重税」がもたらす社会的な弊害に関する議論は、全くなかった。
これは、ある意味では、当然のことで、イギリス社会が「ゆりかごから墓場までの」手厚い福祉国家を実現しようとしたとき、これに反対する議論がなかったという認識が、日本社会では通用してきた。
この点では、情報不足の欠点は否めない。いわば、常識としての「当たり前」であったのと同様であろう。
この「当たり前」に疑問を呈するとは、と、受け取られたに違いはないと思われる。
1940年代や1950年代に、クラークは、重税の結果として、多くの市民が「選択の自由を奪われる」と主張したのであったが、日本社会では、市民社会の枠組みが新憲法によって、漸く、スタートしたばかりのことであったので、「選択の幅を自由に人間が持つ」などの問題点に気づくには困難が多かった。
(©Ikegami,Jun.2023)