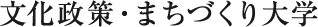総合学術データベース
総合学術デ-タベ-ス:個人別研究内容(14)十名直喜 先生;「働・学・研」協同の理念と半世紀の挑戦―仕事・研究・人生への創造的アプローチ―:内容紹介;池上惇
私の恩師から学んだこと
わたくしは偶然に母校に職を得た。
それは、なぜなのか。
今から考えても不思議なことである。
わたくしは、大学教師になるよりも、大学院で学習・研究して、著作者として自立する研究人を目指していた。
ところが、そういう進路を考える人間が、大学の教師としてふさわしいと考えた大学教授がおられた。わたくしの恩師、豊崎稔先生である。
先生は、徹底した「現場主義」の研究スタイルで、日本機械工業の基礎構造を解明された。そして、その研究の中に、日本機械工業の決定的な弱点を発見されていた。それは、日本の大規模企業が機械工業を発展させるにあたって、「欧米技術の導入」を中心とし、可能性の大きな、日本固有の産業イノベーションの方向を研究開発しなかったからである。
この弱点を発見されたことを、当時の学術界は高く評価した。しかし、時の政府は、太平洋戦争を準備していたので、このような発見は対米戦争の妨げになると判断したのであろう。先生の学位論文は、認められなかったといわれている。戦前は、学位も「官許」であったのだ。
先生は、大学を辞されて大阪商工会議所に移られた。戦後になって、学位が認められ、京都大学教授として招聘されたそうだ。先生は、ご自分のことは一切わたくしたちには語られなかったので、「そうらしい」としか、言えないが、戦争経済に突入するころであれば、ありそうな話であった。
十名先生と、恩師との重なり
十名先生の「働・学・研」協同の理念と半世紀の挑戦―仕事・研究・人生への創造的アプローチ―を拝読していると、恩師、豊崎先生のお姿と重なってくる。
敗戦後、日本社会は、平和憲法の下で、民主主義と、公正競争秩序(独占禁止法など)をもつ、市民社会となるはずであった。
明治維新の時、沈黙を余儀なくされた植木枝盛の日本国憲法草案など、多くの業績が評価され、スイスなどの恒久平和の実績もあって、日本は、世界で最も進んだ民主主義と、公正競争の社会として、再建されるはずであった。
ところが、1950年に朝鮮戦争がはじまると、日本占領軍であったアメリカ合衆国の対日方針が根本的に転換される。日本を再軍備して「アジア人をアジア人と闘わせる」方針が打ち出され実行されたのである。
それでも、日本市民は必死に抵抗して、平和憲法を維持した。しかし、経済面では、旧財閥系の企業が復活を認められ、独占禁止法が緩和されて、独占企業が再生してきたのである。それでも、独占禁止法そのものを廃止することはできなかった。日本の零細中小企業が、すでに、再生していて、緩和はできても、廃止は不可能であったのである
このような状況であったから、復活した日本の大規模企業の中には、雇用した人々が自由に研究活動をして、それを基礎に、改善提案などを積極的に行うことを嫌悪する雰囲気があったように思う。
当時は、上意下達が普通であったから、自由を求める人間というのは、大企業秩序を乱す攪乱者とみなされやすいといえるかもしれない。
現在では、大企業の不祥事などが続発して、法を遵守するのは大企業の「当然のモラル」となっているが、それでも、事件が続発する時代である。
十名先生が、日本の大企業に勤務されて、不自由な目にあい、自由な研究が困難となる状況に直面されたとき、先生は、敢然と、困難に向き合われて、企業から与えられた現場の実態から研究を深められた。そして、自由な研究の場を確保する努力を継続された。
それは、当時の雰囲気としては、息が止まるくらいの大変なことであった。
ところが、そのとき、私は教師として何もできずにいたが、彼の属した日本の職場では、かなり多くの方々が、彼の自由な研究を支持してくださったのである。教師にとってみると、これほど、感謝すべきことはない。
おそらく、職場の雰囲気が影響したのであろうと思われるが、十名先生が、大企業の了解を得られて、京大の社会人大学院で、自由な研究を継続されることになった。幸いなことに、私が学部長時代に文部省が社会人大学院を奨励してくれていて、京都大学大学院経済学研究科に現代経済学専攻という社会人コースができていたのである。
私は、有頂天になって、休日も返上して、授業や研究会を行っていた。これは、十名先生ばかりではない。飛行機でやってきて、飛行機で帰ってゆかれることもある。恐ろしいことであるが、これが実態であった。
しかし、これらの授業や研究会で、私の学識は飛躍的に豊富になり、真実に触れる機会が拡充された。わたくしのほうこそ、社会人大学院生にお礼を言わなければならない。
実は、社会人大学院生がご苦労されているとき、教師は、何もできない。だた、はらはらしたり、上司とうまくやってくれるよう、祈ることしかできない。
無力そのものであるが、社会人諸君はしっかりしておられて、学習・研究の機会を有効に生かされ、博士学位論文を、社会人以外の大学院生よりも、早く完成され、学位を得られた。これは、教師の指導力ではなくて、自分で自分の道を拓く決意によるものと思う。
自己の可能性への挑戦は、貴重な成果を生むのである。
働きつつ学ぶ研究人こそ「産・学・公共人材」の核心
わたくしは、もともとが、「自由業としての研究者」を目指していたので、このような力量を持つ研究者の増加を期待していた。大学院学生が指導できるようになって、彼らに、「大学教師として就職することを期待するな。自立して、研究成果でメシを食え」などと、無謀なことをいうものだから、ずいぶん、嫌われた。しかし、なぜか、「あの教師は指導に熱心らしい」という評判があって、不思議に大学院学生が多く、多くの学位論文を読ませていただく機会を得た。これも、私にとっては、かけがえのない、成長の機会であった。
十名先生は、社会人大学院生の研究交流の場を生み出す名人であった。わたくしは、ゼミナール終了後に、日仏学館でワインを御馳走するだけの教師であったが、社会人大学院生は、初めての経験で、ある意味では、「十名先生」であった。
「働・学・研」協同の試みと原型づくり
十名先生は、製鉄所21年、大学27年、合せて48年の勤務を終えられ、2019年3月に定年退職を迎えられた。この間に、「働きつつ学び研究する」(すなわち「働・学・研」協同の)生き方を心がけて、自分なりのスタイルをつくり出してこられた。驚くべきことであるが、今から考えると、「自分の可能性への挑戦」こそ、あらゆる困難を乗り越えて一歩一歩、たくましく生きてゆく秘訣なのだろうと思う。 先生は、半世紀近くにわたる「働・学・研」協同の学習・研究システムを開発された。
先生によれば、それには、3つの原型(いわゆる「型」)がある。
1つは、働きつつ学ぶ、労働する人間が自分で、自分の仕事を研究するという研究者モデルである。わたくし自身が、十名先生から鉄鋼現場、溶鉱炉は「ハイテク」の塊であることを教えられた。最先端の情報システムが、生かされていたのである。この現場の研究を進められたことが、普通の学者にはできない、「日本鉄鋼論」を生み出す基礎にあった。
そして、当時は、多くの論争の渦中にあった、「日本技術論」を深く研究されていたことも、十名直喜[1996.4]『日本型鉄鋼システム―危機のメカニズムと変革への視座』同文舘、十名直喜[1996.9]『鉄鋼生産システム―資源、技術、技能の日本型諸相』同文舘、などの名著を生み出す基礎となった。
この意味では、十名先生の研究スタイルは、技術論という理論研究と、日本鉄鋼業論という「現場の実態」が結合されていて、素晴らしいと思った。わたくしなどには到底できない、深くて総合的な研究である。
2つには、社会人大学院で博士論文をめざす社会人研究者モデル、
そして、3つは名古屋学院大学での博士論文指導を軸にした社会人研究者育成モデル、であった。
「そこから、多様な社会人研究者モデルが輩出する」というのがご主張である。
先生ご自身の言葉をお借りすると、「浅学非才にもかかわらず、こうした原型づくりに関わることができたのは、なぜか。まさに、それぞれの課題が社会的に浮上した時期に、遭遇できたことである。そして、(正面から課題に向き合うなか)多くの優れた先達や仲間に出会い、そうしたコミュニティで学ぶことが出来たことが大きい。その多くは、「時の利」「人の利」「地の利」に恵まれたことに与っている。そうした中で可能となった挑戦であったといえよう。」と述べられている。
私の感想では、厳しい職場と、自由な学習・研究の場を往復しながら学習できるという状況が、戦後の日本社会では、存在していたということが、非常に大きいと思う。
これは、ある意味で、「今できること」である。
その意味では、社会人各位にお勧めできる新たなライフ・スタイルであった。
指導よりも助言を
十名先生は、これまでの経験を総括されて次のように述べられている。
「現場情報と専門知識に富む社会人に対しては、「指導」という上からの目線ではなく、一緒に考え学ぶという同じ目線、いわばスタンスの転換が求められるように思われる。これまで「博論指導」あるいは「研究指導」という表現で通してきたが、「指導」というより「助言」の方がマッチしている。研究アドバイザー、研究ガイド・伴走者といえるかもしれない。
社会人研究者の多彩な現場経験と目を通して、多様な現場を追体験し、一緒に学び研究する。そのような得難い機会を得ることができるのである。大学という教育現場、そして机上の研究を越えて、現場の最前線の息吹に触れつつ共に学び研究することができる。まさに、宝石の如き時空といえるかもしれない。博論指導の醍醐味も、そうした中に潜んでいるといえよう。
博士論文指導、博士号の授与が、大学にとって持つ意義もそこにある。現場と大学のつながりを深め、相互の活性化を通して、現場のイノベーションを促し、大学の品格を高める。「働・学・研」融合は、そのような好循環をうみだす力になるであろう。」
これは、心から共感できる。的確な総括である。
二宮尊徳の文化的伝統を今に生かす
以下は、十名先生の二宮尊徳評価である。
「日本には「働・学・研」融合の思想と実践の伝統が脈打っているが、その元祖とみられるのが二宮尊徳である。
江戸後期の篤農家で報徳思想を提唱した二宮尊徳は、土から萌え出た(土着かつ)独立の思想家であった。職業としての学者のみちに程遠い生活にあって、その鋭い自然観察と実務家が持つ徹底的な合理主義によって、新しい道を切り開いてきた。立派な農民として成長することが、思想家・尊徳の誕生を可能にしたのである。彼の自然や歴史を見る目は、弁証法的かつ発展的であった。彼の仕法は、自らの経験に基づくものであるが、単なる現場の経験主義にとどまらず、それを裏づける独自の哲学があり、歴史的科学的な調査があった。その実行にあたっての計画は精密に組み立てられていたのである[1]。
生きる哲学、平凡な道徳の提唱・実践とその伝播力、人倫に適う経営革新によって、605村の復興、数千・数万町歩の開墾を行うなど、尊徳はスケールの大きな実業家であり、静かなる革命家でもあった。
そうした思想と実践を生み出した根底には、古典(『大学』など)を肌身離さず野良仕事に明け暮れる青年期の金次郎像[1]、さらに生涯を通しての「働きつつ学び研究する」スタイルの徹底した実践と積み重ねがある。
この19世紀日本の卓越したモデルは、まさに「働・学・研」融合の21世紀モデルでもある。人生の質的変革を担う社会人研究者像の先駆け、みなすことができるのではなかろうか。」
先覚から学ぶ謙虚な姿勢。これも、十名先生の研究スタイルであった。
(©Ikegami, Jun 2020)