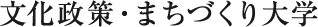お知らせ
総合学術データベース:時評欄(71)ホ-ムペ-ジ用;池上惇「高校生が投資を学ぶとは -金融教育の必修化を前にして」
高校生に対する金融教育の必修化
『日本経済新聞』2022年2月5日付、夕刊は、1ページ、冒頭に、「高校生、投資を学ぶ」「金融教育 今春に必修化」「プロが出張授業/まず 教師に知識」などの見出しを掲載した。
この記事の内容を、端的に要約するのは困難であるが、背景には、次のような要因があると判断し得る。
第一には、成人年齢が従来の20歳から18歳となり、高校生にも、親から自立して「契約関係を事業者と取り結ぶ権利」が発生したことである。すでに、金融庁が、2021年から、ユ-チュ-ブで、「高校生のための金融リテラシ-講座」を開設し、「主な金融商品の特徴や経済全体とのつながりなどを」解説していること。また、同庁のホ-ムペ-ジで公開する副教材では、毎年の投資額や目標額などを入力すると、複利効果でどれだけ資産が増えるかを、シュミレ-ションできる。
実際に、ユ-チュ-ブで、教員用の映像・解説を見ると、この講座は、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことを契機として作成されており、解説内容も、貯蓄や預金などを批判する調子ではなく、リターンとリスクの関係にも深く言及していて、投資活動を個人に対して推奨する内容ではない。
第二には、金融広報中央委員会による、2019年の調査に基づく国際比較の数字があげられ、日本と米国を比較すると、「学校で金融教育を受けた人の割合は、日本、7%、米国、21%である。また、金融知識に自信があると答えた割合は、日本、12%、米国、76%であり、「金融教育のおくれが貯蓄から投資への流れを抑える1因となっている」とのコメント(ファイナンシャルプランナー五十嵐修平氏による)が付されている。
この調査は、18歳以上の個人に関する金融リテラシーに関する総合的な調査で、全国の18~79歳の個人25,000人 を対象とし、インターネット・モニター調査である。この内容も、金融教育のおくれだけを強調したものではなく、金融リテラシー(お金の知識・判断力)の現状把握を目的とする大規模調査であり、その一部で、金融教育のおくれを日本社会の特徴として指摘しているに過ぎない。
日本における金融教育に必要なものを考えるには
金融庁による講座の開設やや金融広報中央委員会による「お金の知識・判断力」の調査を通じて、「18歳からの新大人」となり、契約当事者となる市民を対象とした、「金融教育」が提起される経過を見てきた。
論者の中には、「この機会に、貯蓄から投資へ」と、日本市民を導きたいというご意向も見え隠れする。
しかし、これまでも、「貯蓄よりも株式投資を」という主張は、第二次世界大戦後、日本の社会では、繰り返し提起されては、挫折してきた経過もある。その理由は、大きく見れば、「日本における株式市場の不確実性」つまり、リスク・リターンの計算以上の大変化が存在して、大衆投資家に莫大な損害が発生し、これが、「金利が低くても元本だけでも保全したい」という世論につながっていたとみることもできる。とりわけ、バブル崩壊期の記憶は多くの大衆投資家を傷つけてしまったのではないか。
このような、ある意味では、無理な期待を金融教育にかけるのは、日本市民の合意が得られないように思われる。
同時に、金融教育の提起は、「生涯にわたる資産形成の重要性」を高校生に提起した。このような視点は、「その日暮らし」の家計のやりくりに追われている状況では、考える機会が少なく、学校で教える重要課題の一つであることに違いないであろう。
では、高校教育に金融教育を導入するとして、その内容や、名称は、どのようにすることが、事実に合致し、市民の合意を得られるのか。
改めて検討する必要があるのではないか。
「事実に合致し、市民の合意が得られる金融教育」をめぐって
市民として生きてゆく上で、「事実に合致し」「市民の合意が得られる」ことこそは、公共的な活動における原点であり、この点に異論はないと判断し得る。
その際、注目されるのは、貯蓄という経済行為は、高額所得者から中産層、低額所得者を含む、全市民からの資産を金融組織がお預かりして運用するというルールが、習慣としても、法律としても、定着しているという事実である。
さらに、金融組織が市民から提供される資金を運用するときには、民間企業などへの株式や社債への投資だけでなく、国債や地方債などの公共団体などが発行する「確定利付け」の債務証書が最大の比重を占めるという事実がある。
とりわけ、国債の発行と引き受けは、国家予算上の最大収入項目となっていて、日本では、OECD諸国中でも異常なほどに比重が高く、国の一般会計予算のうち、二〇二一年度の国債収入の割合は、三分の一に達している。租税などは、三分の二にすぎない。
そうなってくると、金融といっても、財政と一体化していることになり、財政における納税行為が、アメリカの独立革命をはじめ、多くの国々で、市民主権を確立する基盤となってきた経過を見るとき、財政と金融とは密接な関係がるとの前提に立って、高校生への教育内容を考えてゆく必要があるのではないか。
すなわち、財政と同じように、金融も、同時に取り上げることが教育においても求められる可能性がある。
例えば、財政に比べて、金融は、自由な取引関係の形式をとっているとしても、何らかの意味で、市民主権の基礎を持っていると考えざるを得ないという面もある。
すなわち、財政は納税の責任ということで市民が主権者として納税し、政府は徴税権をもって強制でき、これによって、公務を支えているのに対して、金融は、強制的に徴税するのではなく、市民が自発的に自らの責任で貯蓄し、金融組織が自由に運用しているにすぎない。
しかし、国債収入の比重が大きくなれば、納税者への依存度が大きくなるだけでなくて、次世代の家計収入までもが、国の借金の返済に充てられることとならざるを得ない。
そうなってくると、本来は、自由な民間経済の解説や解明であるはずの金融教育の中にも、財政との関係や「自由な経済活動にとっての制約を加えるもの」として、財政と金融の関係を導入する必要が出てくる。
また、第二次世界大戦後、日本の物価が700倍にも高騰するといった、「ギャロッピング・インフレーション」の場合には、国家が借金の返済能力を失い、日本銀行から紙幣を発行して、国債を買うなどの非常手段をとる。
その時には、古い紙幣は価値を失い、新たな紙幣を発行して、交換比率を決め、預金を封鎖して、事実上、無価値にしてしまうなどの厳しい措置が採用された。当時は、アメリカの調査団が日本経済を診断して、増税政策を採用させ、同時に、超均衡予算を組ませて強引に赤字を解消させた。
この経験からすれば、国家が破産するときには、市民の資産を犠牲にしてでも、予算を均衡させる強制的な措置が採用される可能性が高い。
本来は、財政や金融は、市民生活を支え、あるいは、国民経済を支えるためにあるはずのものである。しかし、国家破産となれば、市民生活に有害な影響を与える強制的な措置をとるならば、市民のための、財政や金融ではなくなる。財政や金融が市民の上に立って、市民に犠牲を強制する。
本来、このようなことは、絶対に許せないはずではあるが、緊急事態となれば、通ってしまうのである。
同じような事態を招かないためには、新たな創意工夫が求められる。
例えば、国家破産が迫ってきたときには、日本の市民生活を守るために、納税者主権や金融主権を生かした、国家破産からの救済策を準備しなければならないのではあるまいか。
このような救済策は、国家破産というときには、国家に依存するわけにはゆかないから、市民が主体的に判断して、市民の合意のもとに、事実に合致した、民間主導の動きを生み出すことになるのではないか。
日本社会では、幕末、維新のころに、二宮尊徳が提起した、国家破産救済策の経験があり、「尊徳仕法」と呼ばれていた。これは、尊徳自身が自分の財産を土台金として寄付し、これに、地元資金を積み上げて「地域再生ファンド」を形成する。また、大正デモクラシ―期には、大阪市が寄付金を集めて財政危機に対処した経験もある。これらの経験は、「民間主導の寄付行為を基軸とした基金形成など」によって国家破産に備えることが有効であること。これが示唆されていた*。
高校生の金融教育にも、このような経験を伝え、教師も生徒も、ともに、「答えのない答え」について考えることが必要ではないかと考えられる。そして、このような「自由な討論の場づくり」こそが、これまで、日本社会ではなかった、新たな教育の機会を生み出すのではないか。
*尊徳の仕法については、池上惇『文化と固有価値のまちづくり』水曜社、2012年、同『文化資本論入門』京大学術出版会、2017年、同『学習社会の創造』京大学術出版会、2020年などを参照。なお、森・海・里の連環学については、田中克監修『命の循環「森里海の現場から』花乱社、2022年を参照。
(©2021、Jun、Ikegami)